2026年1月30日


初回カウンセリングをご希望の方はこちら
オンラインカウンセリングログイン
資料ダウンロード
タグ : 本山真(精神科医師・産業医) , 産業精神保健
2025年10月17日
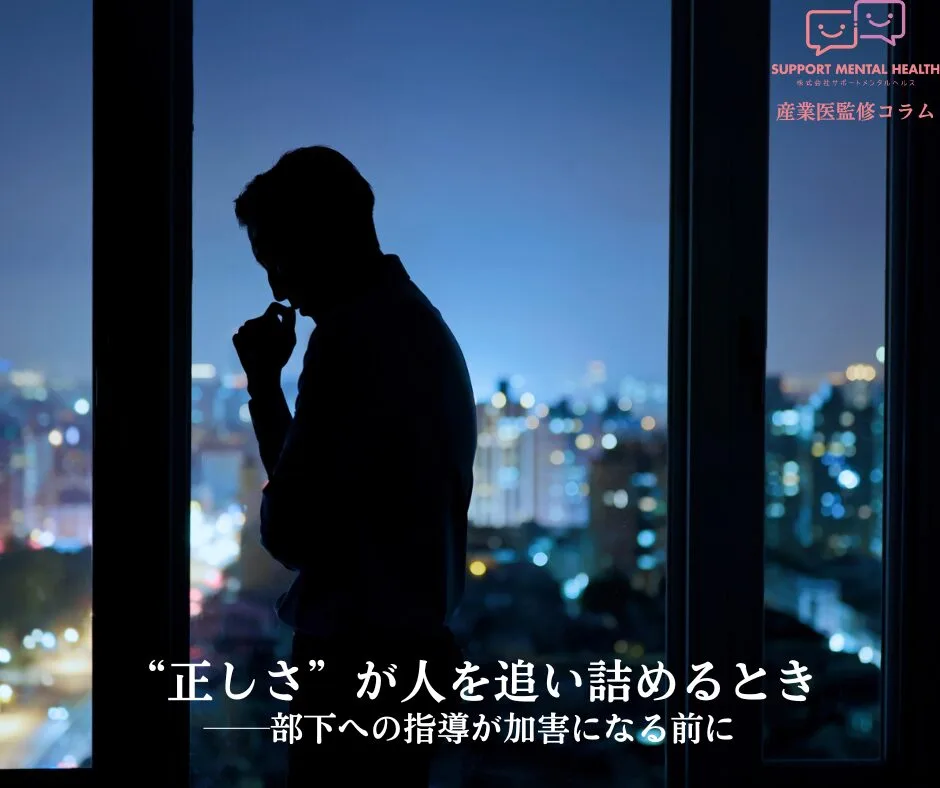
目次
株式会社サポートメンタルヘルスは”働く人を応援するメンタルクリニック”を運営する医療法人が母体です。医療機関におけるメンタルヘルス対策のノウハウを以て、全国の中小企業をサポートいたします。 株式会社サポートメンタルヘルスでは、メンタルヘルス専門職による”中小企業のメンタルヘルス対策個別無料相談会”(web開催、日時は応相談)を実施しております。従業員のメンタルヘルス対策にお悩みの経営者様、人事ご担当者様、まずはお問い合わせフォームよりお申し込みください。
お問い合わせ、取材のご依頼、協業のご提案などにつきましてはお問い合わせフォームよりよろしくお願いいたします。 |
職場で起こるメンタル不調の相談。その背景を丁寧に聞き取っていくと、しばしば「上司からの“正しさ”の押しつけ」が影を落としている場面に出会います。
「部下のためを思って」
「本人の将来を考えて」
その気持ちに嘘はない。
けれど、まっすぐな善意ほど、時に人を傷つけることがあります。
管理職にとって避けて通れない「指導」の場面。そこに潜む、無自覚な“加害”性を見つめることは、自分自身を守ることにもつながるのです。
例えば─
「遅刻を繰り返す部下に、厳しく注意した」
「報連相ができない若手に、根気強く指導した」
どちらも、管理職として当然の対応のように見えます。けれど、部下が精神的に追い詰められた末に休職したとなれば、どうでしょうか?
「注意しただけなのに、なぜ?」
「甘やかしたら本人のためにならない」
そんな疑問や苛立ちが浮かぶかもしれません。しかし、“正しさ”は常に一枚岩ではありません。その“正しさ”が、部下にとって「耐えられないプレッシャー」になることもあるのです。
人は、誰かに期待することで、その人の行動に意味づけをします。「期待しているからこそ厳しく言う」という指導は、裏を返せば「こうあるべき」という枠にはめる行為でもあります。そこには、“正しい部下像”というラベリングが無意識に働いていることもあります。
これらは一見すると社会人として当然の姿勢に思えますが、すべての人が同じように振る舞えるわけではありません。
背景には、発達特性・家庭環境・トラウマ・病気など、様々な事情があるかもしれないのです。
「これが正しいと思うことを伝える」
これは管理職として、重要な役割です。
しかし、その“正しさ”が相手に届かない、あるいは届いても心を壊してしまう。
そんなとき、いったん「自分の正しさ」を脇に置いてみる勇気も必要です。これは「指導をやめる」「放置する」ことではありません。むしろ、より丁寧に、より双方向的に関わるということ。
問いかけることで、相手の中にある“正しさ”も尊重できる関係性が生まれます。
ここで、もう一つ大切な視点を。
部下を守ることに必死になるあまり、自分自身が疲弊していないでしょうか?
これらは一見「良い上司」の行動に思えるかもしれませんが、実は危険信号でもあります。“部下を守る”という使命感が、“自分を壊す”ことにつながってしまっては本末転倒です(関連:部下・同僚への配慮|厚生労働省こころの耳)。
メンタル不調を抱える部下を支えるには、次の3つの視点が有効です。
無理に変えようとせず、「ここにいていい」と思ってもらう関係性を。
本人のペースや文脈を尊重した対応が求められます。
産業医、外部相談窓口、人事など、多様な支援資源を活用することが必要です(こちらもどうぞ:精神科産業医監修|産業医面談のメリット・デメリットを解説)。
私たちは「相手のために」と思って行動します。
けれど、その善意が相手にとって負担になることがある。
だからこそ、独りよがりにならないよう、チームで対話することが大切です。
「この対応、どう思う?」と、同僚と話せる風土があるか。「自分がつらい」と言える職場になっているか。それが、組織のしなやかさであり、強さです。
“正しさ”に追い詰められてしまう職場が増えています。その火種が、誰かの善意から生まれていることも珍しくありません。
「正しいことをしているはずなのに、なぜ苦しいのか」
そんな違和感を覚えたときこそ、立ち止まるチャンスです。
「正しさ」を問い直すことは、自分自身を大切にするということ。
あなたが壊れず、部下も潰れない職場を目指して。