2025年12月26日


初回カウンセリングをご希望の方はこちら
オンラインカウンセリングログイン
資料ダウンロード
タグ : 産業精神保健
2025年5月5日
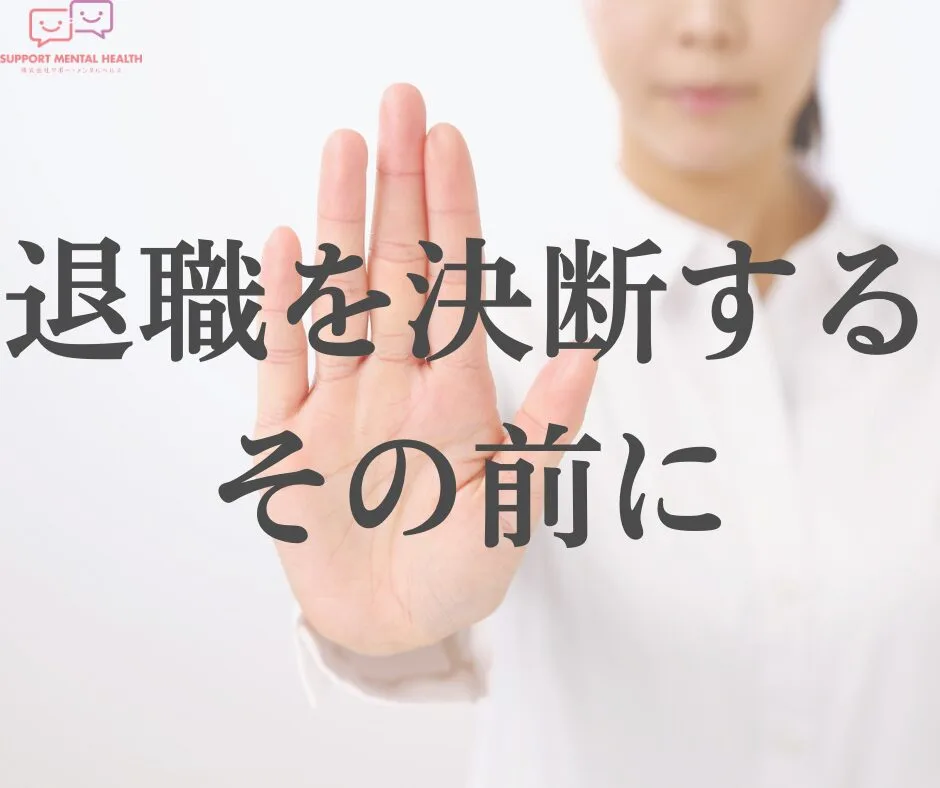
目次
私は、メンタルヘルス支援職として勤務をしています。日々、心の不調を抱える方々の声に耳を傾けながら、一人ひとりの「今」と「これから」に寄り添う支援を続けています。
ここ数年、「退職代行」という言葉を目にする機会が増えてきました。ご相談を受けるなかでも、「会社にはもう行けません」「自分では言えないから代わりに手続きを進めてもらいました」といったお話を聞くことが増えています。退職という決断は、それだけでその人の背景や状態を語り尽くせるものではありません。でも私は、この「退職代行」という現象の背後に、もっと深く、繊細な心の動きがあるのではないかと感じています。
株式会社サポートメンタルヘルスは”働く人を応援するメンタルクリニック”を運営する医療法人が母体です。医療機関におけるメンタルヘルス対策のノウハウを以て、全国の中小企業をサポートいたします。 株式会社サポートメンタルヘルスでは、メンタルヘルス専門職による”中小企業のメンタルヘルス対策個別無料相談会”(web開催、日時は応相談)を実施しております。従業員のメンタルヘルス対策にお悩みの経営者様、人事ご担当者様、まずはお問い合わせフォームよりお申し込みください。
お問い合わせ、取材のご依頼、協業のご提案などにつきましてはお問い合わせフォームよりよろしくお願いいたします。 |
メンタルヘルス情報配信中!友だち登録どうぞ!
「仕事を辞めたい」という思いには、たくさんの理由が絡んでいます。人間関係がつらい、仕事量が多すぎる、自分の存在が見えなくなるような感覚……。いずれも、表面的な説明の奥には、その人の価値観や生活、過去の経験が複雑に絡んでいます。
厚生労働省の「労働安全衛生調査(令和4年)」によると、メンタルヘルス不調により1か月以上の休業や退職をした労働者がいる事業所の割合は9.2%。この数字は、決して小さなものではありません(※1)。でも、統計には表れない「もう限界だった」「とにかく逃げたかった」という気持ちを、私たちは見落としてはいけないと思うのです。
メンタルヘルス不調が続くと、次第に「今すぐ抜け出さなければ」と感じるようになります。日常の些細な刺激が負担に感じられたり、周囲の言葉が遠く思えたり、自分の判断が正しいのか不安になったり――。こうした状態のひとつに、「心理的視野狭窄」という現象があります。心が疲れていると、思考の幅や柔軟性が損なわれ、視野が狭くなる。選択肢が「辞める」か「耐える」しか見えなくなってしまう。
この状態は、誰にでも起こりうるものであり、決して弱さや甘えではありません。むしろ、心が生き延びようとしている自然な反応です。ただ、そんな時に大きな決断を下すことは、時にリスクを伴います。未来を見通す力が弱まっていると、後になって「本当は他の選択肢もあったかもしれない」と思うこともあります。
退職を決断する前に、ぜひ一度、立ち止まってみてほしいと思うのです。
たとえば、多くの企業には「休職制度」があります。医師の診断書があれば、一定期間仕事から離れて、治療に専念することができます。さらに、健康保険に加入していれば「傷病手当金」が支給される場合もあり、一定の経済的支えになります(参考:精神科医監修:適応障害と診断され休職をすすめられたらどうすればいい?)。
こうした制度を利用することで「仕事を完全に辞める」以外の道も見えてくるのです。ところが、実際にはこうした制度の存在や使い方を知らずに退職してしまう方も少なくありません。また、必要に応じて、産業医やカウンセラーなどの専門家に相談することで、気持ちの整理や見通しを立てる支援を受けられる場合もあります。
「辞めることが悪い」と言いたいのではありません。けれど、選択肢が複数あると知った上で選ぶ「辞職」と、追い詰められた中で選ぶ「逃避」とでは、同じように見えてその意味は大きく異なるのです。
退職代行というサービスは、確かに必要なものです。会社と連絡を取ることすら難しい状況にある方にとってサービスは安全な出口のようなものかもしれません。だからこそ、退職代行サービスを提供する皆さんには、「今、この方は本当に退職を望んでいるのか?」「心理的に極限の状態ではないか?」といったまなざしを期待したいのです。
ほんの一言、「休職制度をご存知ですか?」「専門家に相談するという選択肢もありますよ」と伝えるだけでも、利用者のその後の人生に違いが生まれることがあるのです。それは、代行業務の範囲を超えた関与かもしれません。でも、社会的意義を高めるという点では、こうした支援のあり方が、退職代行サービスの信頼性や価値を高める未来につながっていくのではないかと感じています。
メンタルヘルスの支援を行う中で、私はいつも「この方はどのような暮らしを望んでいるのか?」という問いを大切にしています。私たちが向き合っているのは、「病気を治す」ことだけではありません。「働く」「休む」「つながる」「支える」「役割を果たす」――それらの全体が、その人の“生活”をかたちづくっているからです(関連項目:困りごとの源泉の変遷|医学モデルと社会モデルの違い。BPSモデルそして生活モデルへ)。
仕事を辞めることは、その一部を手放すということです。だからこそ、その決断は、その人の人生の文脈の中で慎重に扱われるべきものだと思うのです。
もし、あなたが今「すぐにでも退職したい」と思っているのなら、その気持ちを否定する必要はありません。むしろ、それだけがんばってきた証なのだと思います。ただ、願わくば、その思いを一度誰かに話してみてほしいのです。信頼できる人にでも、専門職にでも構いません。「話すこと」は、自分の中の視野を少し広げるきっかけになります。
そして、退職代行サービスという選択肢を考えている方には、「辞めることもできる。でも、他の選択肢もある」と知っていただけたら嬉しく思います。そのうえで、「私はこの道を選びたい」と思える選択こそが、自分の人生に責任を持つということではないでしょうか。
あなたの「これから」が、少しでも安心して始められるように。私たち支援職も、静かに力を尽くしていきたいと思っています。
参考資料