2026年2月20日


初回カウンセリングをご希望の方はこちら
オンラインカウンセリングログイン
資料ダウンロード
タグ : TAKUYA(公認心理師・臨床心理士) , 産業精神保健
2025年4月25日
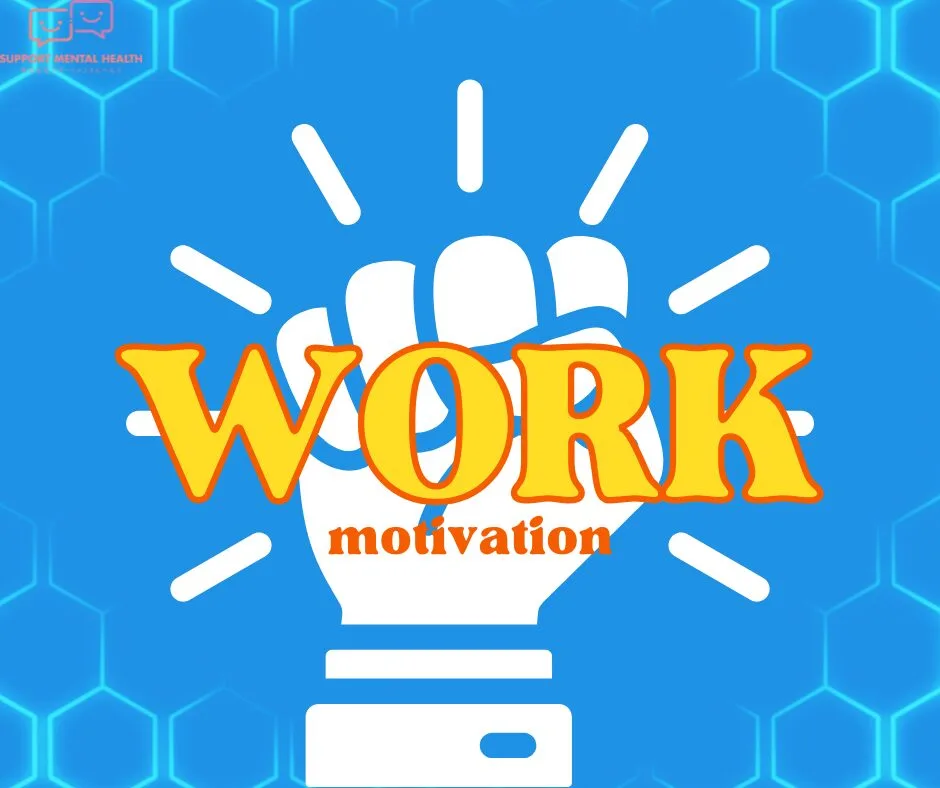
目次
株式会社サポートメンタルヘルスは”働く人を応援するメンタルクリニック”を運営する医療法人が母体です。医療機関におけるメンタルヘルス対策のノウハウを以て、全国の中小企業をサポートいたします。 株式会社サポートメンタルヘルスでは、メンタルヘルス専門職による”中小企業のメンタルヘルス対策個別無料相談会”(web開催、日時は応相談)を実施しております。従業員のメンタルヘルス対策にお悩みの経営者様、人事ご担当者様、まずはお問い合わせフォームよりお申し込みください。
|
メンタルヘルス情報配信中!友だち登録どうぞ!
「やる気」や「意欲」の意味で用いられるモチベーション。仕事のモチベーション,家事のモチベーション,勉強のモチベーションなどなど。何をするにしても,その行動に先立つものはモチベーションです。
モチベーションは日本語で「動機づけ」と訳される言葉であり,その意味はやる気や意欲を包括した,「目標へ向かう行動を起こし,達成までその行動を持続させる心の動き」を表しています(関連項目:【職場で使える動機づけ面接】ワーク・エンゲージメントを高めるスキル)。
行動のきっかけと持続という点で考えると,モチベーションは日常生活や仕事などのあらゆる活動の原動力として捉えることができます。ビジネスシーンでは,この心理的プロセスをワークモチベーションと呼んでいます。
ワークモチベーションとは「目標に向けて行動を方向づけ,活性化し,そして維持する心理的プロセス」であり,与えられた職務を精力的に遂行する,あるいは目標を達成するために頑張り続けるなど,組織の従業員がある対象に向けて行動している状態を表す概念です。有名なホーソン研究にてその重要性が認識されるようになり,同研究から現在までの約100年の間,様々な研究・検討がなされています。
ワークモチベーションは「方向性(direction)」「強度(strength)」「持続性(persistence)」の3次元から構成されます。
| 方向性…目標をなぜ,どのように成し遂げるかの明確性 強度…目標の実現に向けた努力や意識の高さ 持続性…目標を追求・実現するために費やされる時間の長さや継続性 |
組織構成員のワークモチベーションは,生産性,業績,離職率,人材育成など組織の様々な箇所に影響を及ぼすため,労働力不足が叫ばれている昨今,その重要性はますます大きくなっています。
私たちが「モチベーション」を意識する時,それはおそらく「必要性があるものの,そのモチベーションが無いとき」なのではないでしょうか。現にインターネットで「仕事 モチベーション」と検索してみると「モチベーションを上げる方法」,「意欲が下がったときの対処法」「モチベーションが上がらない方法について解説」等のページが上位に表示されます。また,上記のキーワードでヒットした件数が約2200万件だったことからも,モチベーションへの関心の高さがうかがえます。
約100年前からモチベーション研究がスタートしていたことを考えると,モチベーションへの関心は今に始まったわけではなく,人間は古くから「モチベーションが湧かないこと」に意識があったのかもしれませんね。さて,「なぜ」「どのように」してモチベーションが起きたかという議論はモチベーション研究の中でも関心が大きく,様々な理論が誕生しています。今回はそのうちのいくつかの研究を紹介したいと思います。
内発的動機づけとは,仕事が面白い,好奇心をくすぐられるなど,行動に取り組むことそのものが目的となることを意味しています。対して,報酬や罰などの外的なものが原因となって行動が動機づけられることを,外発的動機づけといいます。内発的動機づけと外発的動機づけは,それぞれ独立しているものではなく,相互に関係することも知られています。有名なものにアンダーマイニング効果,エンハンシング効果と呼ばれるものがあります。
アンダーマイニング効果とは,最初は好きでやっていた行動(内発的動機づけ)に,金銭やご褒美などの物質的な報酬が与えられるようになると,報酬を得ることが目的となってしまい,その後報酬がない場合には,次第にその行動を取らなくなる=内発的動機づけが低下するという現象です。行動そのものが目的だったのに,行動が報酬を得るための手段になってしまう。ということです。
一方,エンハンシング効果とは,言語的な外的報酬が内発的動機づけを高めるという現象です。俗に賞賛効果とも呼ばれます。言語報酬の中に自身の取り組みや結果・過程を評価する側面がある場合,有能感を高めモチベーションが高まるとされています。
ワークモチベーションや職務満足感をもたらす職務特性(仕事内容の特徴)に関する理論です。同理論ではモチベーションや職務満足感に影響する職務特性として下記の5つを挙げています。
そして,スキル多様性,タスク重要性,タスク一貫性は「仕事の有意味感」を,自律性は「仕事の結果に対する責任感」を,フィードバックは「仕事の結果に関する知識」という3つの心理状態を経由し,モチベーションや職務満足感をもたらすことを示しています。
ある行動が結果へつながるという主観的な期待(expectancy)と,その結果の主観的な魅力や価値(誘意性:value)の積によってワークモチベーションを表すことができ,さらに誘意性は,その結果から得られる二次的な結果および二次的な結果の誘意性と,行動の期待が二次的な結果を得る上でどれくらい役立ちそうかという主観的な程度(道具性:instrumentality)の積によって計算できる。という理論です。
何言っているかわかりませんね…。しかし,この理論によって説明できる報酬制度があります。それは,歩合制やインセンティブ制と呼ばれるものです。ビールの売り子さんを例にすると分かりやすいかもしれません。
| ある売り子,Aさんがいたとします。 期待 →このAさんが,「一生懸命売り声を上げ,元気に振る舞う」という行動が「ビールが100杯売れる」という結果へつながるだろうという主観的な期待を持っていたとします。 誘意性 →「ビールが100杯売れる」という結果は,歩合給が増える,売り上げのトップになれる,褒められるなどのAさんにとって嬉しい二次的な結果をもたらしてくれます。 道具性 →Aさんがこれら二次的な結果を得るには「ビールを100杯売る必要がある」ため,その結果に繋がりやすい(とAさんが期待している)「一生懸命売り声を上げ,元気に振る舞う」という行動は,Aさんにとってかなり有効そうに見えています。 |
つまり,行動すればするほど魅力的な報酬が大きくなるために,行動へのモチベーションが高くなるというわけですね。
仕事が完了してから,次の仕事に取り掛かる際のモチベーションに関する理論です。仕事に対する自分の仕事量や貢献度(input)とそれによって得られた報酬などの結果(outcomes)の比が,他者の比と同等であれば「公平である」と認知しワークモチベーションを維持し,他者と比較して不均衡であれば,その不均衡を解消しようと動機づけられるとされています。
例えば,自分より仕事量が少ないのに給料が同じ同僚がいる,あるいは,自分と同じ仕事量なのに同僚の方が多く給料をもらっているなど,仕事量から得られた結果の割合が他者より少ない場合(過剰な仕事量)に,「不均衡にある」と感じ,手抜きなどをして仕事量を減らし均衡状態を取り戻すことに動機づけられます。
なお,ここでいう「報酬」とは単に給与を指しているわけではなく,昇進,昇給,福利厚生,称賛,評価など多岐に渡ります。また,他者と比して自身が仕事量に対して過剰に報酬をもらっている場合も不均衡が生じていますが,その状態を解消しようと動機づけられるかについては一貫した結果は得られていません。つまり,inputを増やそうとする人もいれば,そのままにする人もいます。
目標が具体的で,困難で,より自分が関与しているときほど,高いパフォーマンスを導くという理論です。この理論では,人は「ベストを尽くせ」というような曖昧な目標よりも,具体的で困難な目標の方が高いパフォーマンスを発揮することが明らかにされています。ここでいう困難とは,到底不可能なものではなく,達成できるかできないかのギリギリの困難さのことを指しています。複数の研究から,頑健な理論であることが示されています。
近年,目標設定理論は本人が意識することなく周りの環境や刺激によって動機づけが生じるとする自動動機理論への展開も見せています。これは,例えていうなれば,モチベーションに関する言葉を,張り紙など貼って日常的に見ることによって,それに関する非意識的な動機づけがなされ,パフォーマンスが上がるという理論です。業績〇%UPや月〇件達成などと書かれた張り紙もあながち否定できないですね。
「仕事のモチベーションが無い」と一言で言っても,無い理由は人それぞれです。やりがいが無い,仕事が難しい,給料が低い,人間関係がうまくいかないなど,ちょっと想像するだけでもモチベーションが無い理由はたくさん出てきます。
さらに,それらの理由の詳細も人によって異なってきます。「やりがい」を例にとると,それが職務特性的な理由もあれば,公平理論の不均衡を感じている場合もあれば,アンダーマイニング効果が関係している場合もあります。
「モチベーションを上げたい」というときは,なぜモチベーションが無いのかを具体的に詰めていくと,解決の糸口が見えてきます。目標はどう設定しているか,自分にとっての報酬は何か,そもそも自分は自身や周囲に対し狭まった見方をしていないか。そういった過程を歩む際に上記の理論たちは役立ってくれるでしょう。
【執筆】 TAKUYA(公認心理師・臨床心理士)
【監修】 本山真(日本医師会認定産業医|精神保健指定医|医療法人ラック理事長|宮原メンタルクリニック院長) |