2025年12月19日


初回カウンセリングをご希望の方はこちら
オンラインカウンセリングログイン
資料ダウンロード
タグ : ふ~みん(公認心理師) , メンタルヘルス
2025年3月14日
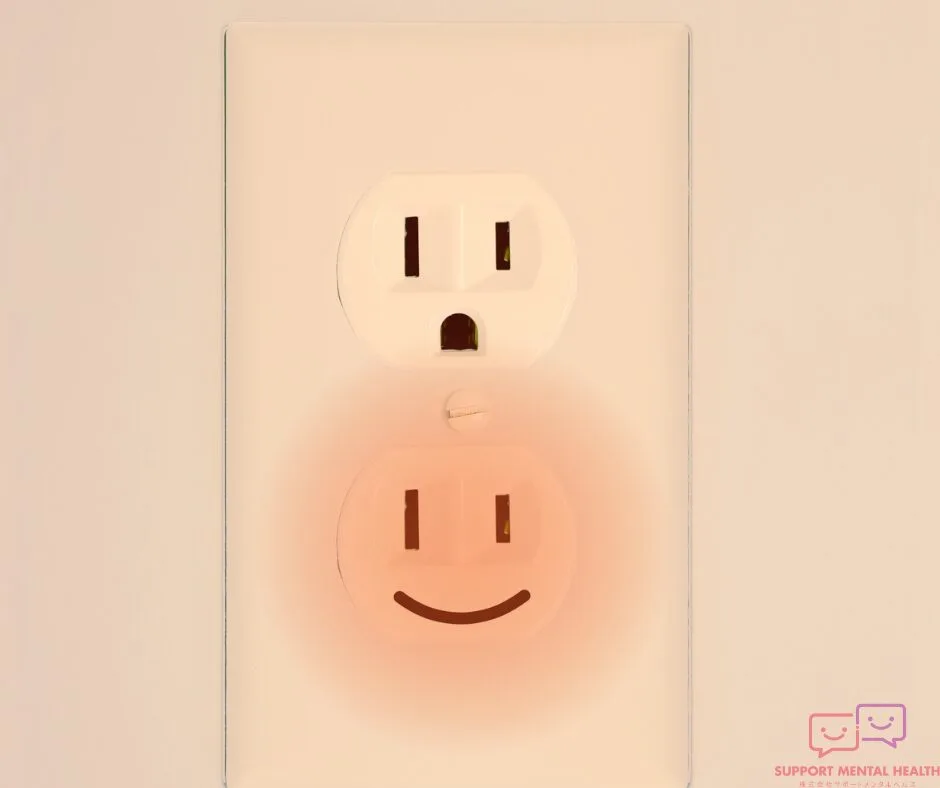
目次
小さい子が大好きなアンパンマン。日本国内はもちろん、海外でも人気を集めている有名なキャラクターですね。教えなくても、親が好きじゃなくても、不思議といつの時代にもアンパンマンに惹かれる乳幼児は多いのです。その理由を探ってみました。
【解説】 ふ~みん(公認心理師)
【監修】 本山真 医師、精神保健指定医、日本医師会認定産業医 東京大学医学部卒業後、精神科病院・診療所での勤務を経て、さいたま市に宮原メンタルクリニックを開院。現在は株式会社サポートメンタルヘルス代表に加え、2院を運営する医療法人の理事長としてメンタルヘルスケアに取り組んでいる。 |
玩具メーカーのバンダイが2018年6月に発表した「お子さまの好きなキャラクターに関する意識調査」(0~12歳の子をもつ人を対象に子どもの意見を入力できるような形式にてインターネット上で実施し、有効回答数800件)によると、0~2歳の層では男女問わずアンパンマンが1位だったそうです。それを踏まえ、アンパンマンを初めて認識し、好きになる年代はおおよそ1~2歳頃と推測されています。
兄や姉がいて既に身近な存在であったり、“小さい子が見るのはアンパンマン”と何となく周囲の大人が動画やテレビを見せていたりと触れる機会がある子もいることでしょう。そうでなくても他のキャラクターよりもアンパンマンが選ばれるのは、その月齢の子どもたちの発達段階と関係がありそうなのです。
小さい子の成長は個人差が非常に大きいためあくまでも標準的な発達を想定してお話ししますが、1、2歳と言えば歩行が可能になり、自分の意思通りにすぐ移動できるようになる時期です。「ワンワン」「ママ」といった簡単な言葉も発せるようになります。2歳に近付くにつれて自我も強くなり、自分の要求を表現できる子も増えてきます。
視覚機能面(視力)においては、生後6カ月頃で0.1~0.2、1歳でも0.3程度とまだそれほど良くありませんが、赤色や黄色などのはっきりした明るい色には興味を示すと言われています。ちなみに、4歳頃になると1.0程度の視力をもつ子が増えてきます。また、このくらいの月齢の子どもは丸い形をした物にも惹きつけられるそうです。具体的な対象年齢は分かりませんが、ファンツ(Robert L.Fantz)というアメリカの発達心理学者は、乳幼児がどのような形を好むのかということを調べる研究を行いました。
すると、
を好む傾向があるという結果が出たそうです。

この結果に示された『曲線で描かれ』、『コントラストが高く』、『人の顔のような図形』と言えば…アンパンマンの顔!
つまり、アンパンマンの丸い目や赤い鼻をはじめとした顔全体の形と色には乳幼児が好む要素が満載だったというわけです。さらには輪郭の中の上方に目、中央から下方にかけて鼻、口があると乳幼児は顔だと認識することが分かっています。確かに、3歳前後の子どもが顔の絵を描けるようになったとき、大きな丸の中に小さな丸を2つ、その下に横線を一本描く、というような形で表現しているのを見たことがある方もいるのではないでしょうか。もちろんそこには眉毛、まつ毛などの細かい部分はほとんど描かれていません。ですからそれが乳幼児にとって顔を認識する最小条件なのですね。
アンパンマンのシンプルで理解しやすい顔のつくりが乳幼児には親しみやすく、それを近くで見ている大人にもかわいらしさややわらかさを感じさせるもののようです。また、3歳頃までの乳幼児が赤色やオレンジ色など暖色系の色を好む(認識しやすい)傾向があることも家政学分野の研究で明らかにされています。主に暖色系で構成されているアンパンマンは乳幼児の目にとまりやすいため、人気者になったのだと考えるとなんだか納得できますね。
ちなみにこちらの研究を行ったファンツですが、心理学の世界では「選好注視法」という実験方法を考案した人物として有名です。これは言葉でのやり取りも視力での測定も難しい乳児が人間の顔を認識しているかどうかを調べるために、人間の顔が描かれた図版と文字や記号のようなものが描かれた図版を同時に提示し、乳児がどちらを長く注視するかを比較したという研究です。
結果として、乳児は人間の顔が描かれた図版を長く見ていたことから、人間の顔とそのほかのものを識別していると考えられました。
ここではこれ以上の説明は省きますので、ご興味のある方はぜひ調べてみてください。
さて、見た目で乳幼児に惹かれる理由は分かりましたが、それだけではなくどうやらその名前にも人気の秘密がありそうです。
人間は発達する過程で言語を獲得していきますが、1歳を過ぎた頃から単語を話せるようになり、2歳前後で二語文(例:ワンワンいる)、3歳頃には三語以上の文を話すようになるのが一般的とされています。中でもア行、マ行、パ行、バ行やワ、ンは発音しやすいと言われています。…お気付きになりましたか?アンパンマン、にはア行、マ行、パ行、ンのすべてが含まれているのです。
「アンパンマン」とはっきり発音することが難しくても「アンアンマン」「パンマン」など、その子なりに見たものの名前を呼んだり養育者などの他者に伝えたりできるようになることは言語によるやり取りの活発化や脳の活性化を促し、乳幼児にとってより興味・関心の深さにつながることでしょう。
このような親しみやすい見た目に発音しやすい名前が合致し、アンパンマンは乳幼児に受け入れられているのかもしれませんね。
最後にもう1つ。
人は特定の刺激(例えば物や人物)を繰り返し見たり、それらと接したりしているうちに、その刺激への好感度が上昇し関心の度合いが高まる特性があると言われています。これはアメリカの心理学者ザイアンス(R. B. Zajonc)によって1960年代に提唱された「単純接触効果」と呼ばれるものですが、近年では心理業界にとどまらずビジネス界でも注目されている概念です(関連項目:オタク臨床心理士・公認心理師は語る。日常に潜む4つの認知バイアス)。
最初に述べたように、もしかしたら兄、姉の影響で物心ついたときから家の中にアンパンマンのおもちゃがたくさんあって、保育園や幼稚園でもアンパンマンの絵本や紙芝居を何度も見たり仲良しのお友達の持ち物がアンパンマンでそろえられていたり、という環境の中で日々アンパンマンに触れていた結果、自然と好感度が上がりいつの間にか好きになっている可能性も大いにあるということです。
このように、乳幼児に受け入れられるいくつもの要素が重なり合い、アンパンマンは長きにわたって子どもたちの人生に影響を与え続けていることが分かりました。誕生した際にこれらが計算されていたのかどうか定かではありませんが、偉大なキャラクターであることは間違いないですね。