2026年2月6日


初回カウンセリングをご希望の方はこちら
オンラインカウンセリングログイン
資料ダウンロード
タグ : かなた(公認心理師・臨床心理士) , メンタルヘルス
2025年5月9日
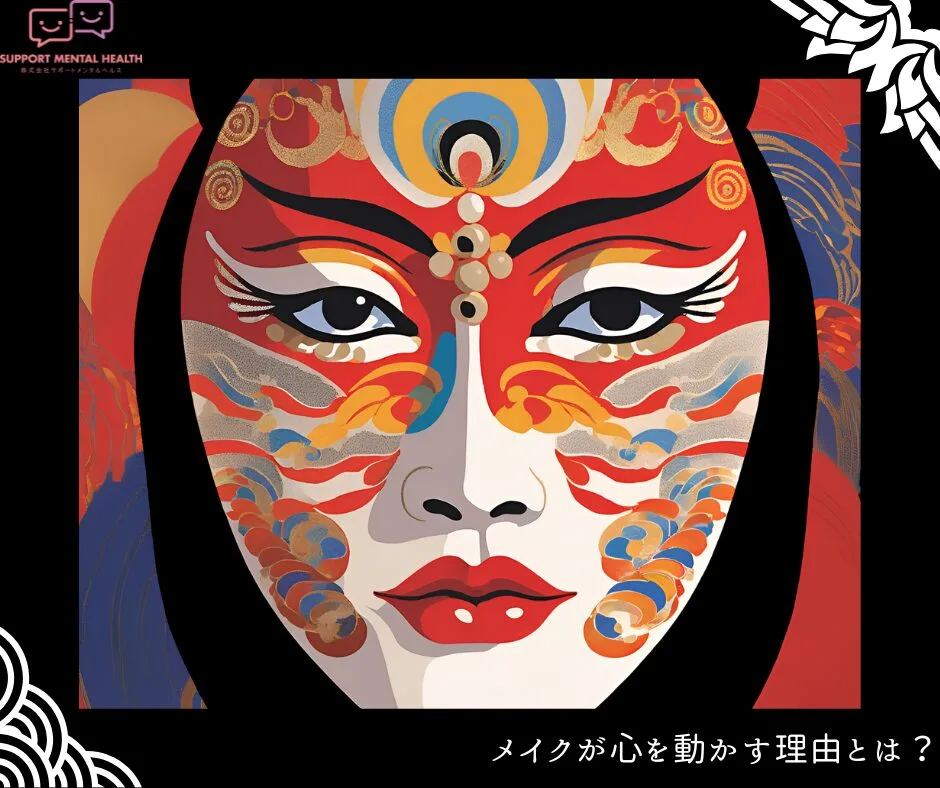
最終更新日 2025年5月9日
目次
みなさんは気分をあげるとき、どんなことをしますか?音楽を聴いたり、お友達や家族とお話ししたり…人によって様々だと思いますが、お化粧をすると気分があがりませんか?ライブやイベントごとなど、お出かけするときには気合を入れてお化粧したりする方が多いかと思います。今回はお化粧に秘められた効果について紹介します!
メンタルヘルス情報配信中!友だち登録どうぞ!
ポーラ文化研究所が行った調査によると、過半数の女性がお化粧をする理由に「身だしなみ・マナー」と回答しました。ほかには「肌の悩みをカバー・ケアするため」、「他の人からきれいに見られたいから」、「自分に自信を持ちたいから」という回答がありました。これらの調査結果から、お化粧をする理由や目的は、自身のこころとからだのため、社会性を保つため、人からの好感度を上げるためなど多様であることが分かります。
では、そもそもお化粧にはどのような目的があったのでしょうか?古代文明までさかのぼると、邪悪な霊や病気を取り払うといった魔よけの力として使用されていたり、若さ、美しさ、社会的な権力など、外見的な強さを示すために活用されていたりしました。昔と今では、化粧の目的や理由に若干の違いこそあるものの、「身を守るため」、「自分を主張・表現するため」という根本的な理由や目的は変わっていない様です。
主に、身だしなみや肌のケアを目的として用いられるお化粧ですが、実際にお化粧をするとどのような効果が得られるのでしょうか?お化粧に関する研究や調査を参照したところ、主に以下のような効果があると示されていました。
|
調べてみて、「こんなに効果があるの⁉」と驚きましたが、「確かにそうかも‼」と感じるものもいくつかありました。例えば、仕事前にお化粧をすることで、気持ちが引き締まり、対人場面でも堂々とできると感じることがあります。
リサーチをしていて個人的に面白いなあと思った研究があります。メイクの効果について生理学的な数値の変化を用いて検討している研究です。
体内の「コルチゾール」(ストレスを感じると上昇し、数分~数時間で元のレベルまで戻る性質がある物質)を指標としてメイクの効果を探索したところ、メイク後に抑うつや不安、疲労、混乱といった感情の得点が有意に低くなり、リラックス度の得点は有意に高くなったという結果がでていました。メイクは直接的に気分を変える効果に限らず、身体の働きとも密接に関係していることがわかりますね。
ちなみに…身体の働きとの関連でいうと、お化粧にリラックス効果があるのは、肌に触れると交感神経が下がる、すなわち副交感神経が優位になり、体がリラックス状態になるからです。
上記で説明したように、様々な効果があるメイクですが、このお化粧を用いて心身の不調を治療する「化粧療法」というものもあります。
化粧療法は、心理的・社会的な健康を向上させる療法です。実際にお化粧をして、自己肯定感などのポジティブな感情を向上する目的で行われています。
高齢者を対象にリハビリの一種として、また、皮膚の疾患やがん患者さん向けにメンタルケアの一種として活用されていたりします。
お化粧をする目的やその効果は、個人差ももちろんありますが、個人差のほかにも左右する要素があります。
1つ目は年代です。高齢の方と比較して、若者の方が、自分を良く見せたり、社会性を保ったりするためにお化粧をしていることが明らかになっています。一方、高齢者はお化粧をすることで「落ち着き」や「リラックス」を得ているようです。これは、高齢者の方が長年お化粧をしていることで、お化粧をしている状態=「いつもの自分」に戻るというイメージが近いかと思います。
このように、年代によって、得られる効果の種類や強弱が違う傾向があります。
2つ目は、「自意識」です。自意識は、化粧の実施や関心を決めるものです。この自意識には、「公的自意識」と「私的自意識」があります。
公的自意識は、自分の外見や他者に対する行動など外から見える自己の側面に対する注意を向ける程度のことであり、私的自意識は、自分の内面や気分など、外から見えない自分の側面に対する注意を向ける程度のことです。この2つの内、公的自意識の高い人の方が化粧の実施頻度が高いことが明らかになっています。
メイクをする意欲が沸かない。それは心身が疲れているサインかもしれません。
実際に、うつ病や統合失調症などの精神障害に罹患すると、身だしなみへの関心が低下する、したいけどできない…といった状況につながることが明らかとなっています。いつものようにお化粧をする意欲がわかなかったり、出来なかったり…思い当たる方がいれば、無理をせず休息をとったり、周囲に相談したり、医療機関に行ったりすることをおすすめします(関連項目:精神科医監修|統合失調症を精神医学の視点から解説!症状・治療法とその背景)。
参考文献
【執筆】 かなた(公認心理師・臨床心理士) 今回はお化粧と心身の関係について簡単にご紹介しました。 効果を知るだけでも、お化粧への心持がなんだか変わったような気がします。何もない日でもお化粧をして気分を上げるなど、リフレッシュの手段としても活用できると思いますので、みなさんもぜひ。
【監修】 本山真(精神科医師/精神保健指定医/日本医師会認定産業医/医療法人ラック理事長) 2002年東京大学医学部医学科卒業。2008年埼玉県さいたま市に宮原メンタルクリニック開院。2016年医療法人ラック設立、2018年には2院目となる綾瀬メンタルクリニックを開院。 |