2026年1月9日


初回カウンセリングをご希望の方はこちら
オンラインカウンセリングログイン
資料ダウンロード
タグ : 田っちゃん@無職生活を経て転職しました!(公認心理師・臨床心理士)
2025年5月16日
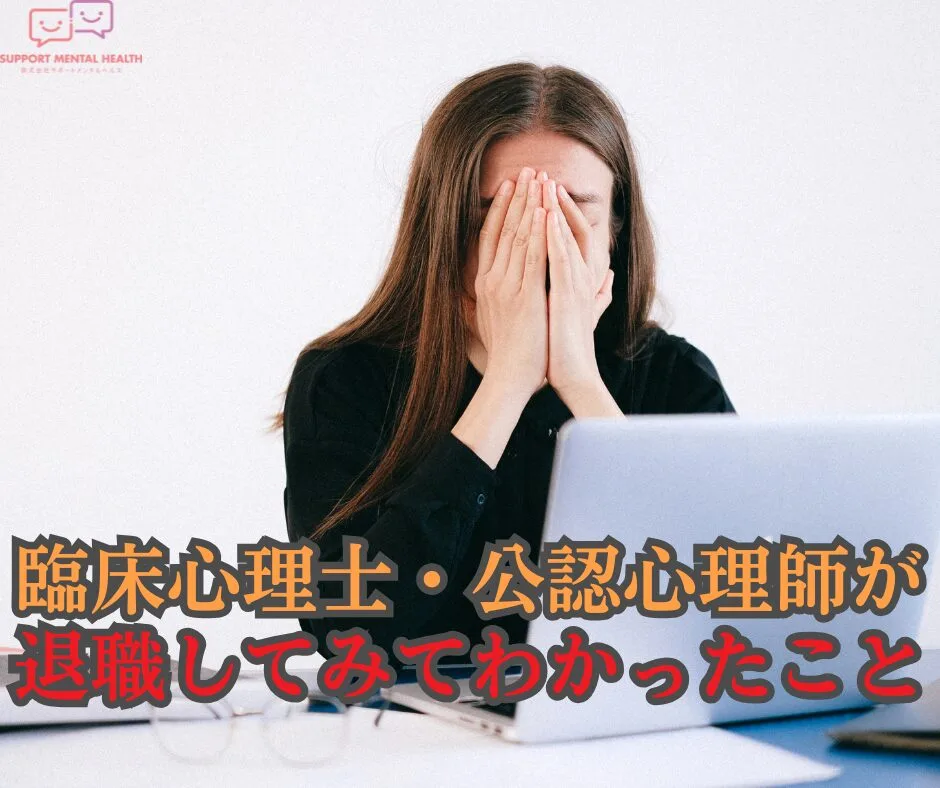
目次
こんにちは、心理職をしている…いや、正確には「していた」者です。そう、無職です。
「無職 どうする」「無職 メンタル やばい」「無職 回復できる?」
まさか自分がこんな検索ワードを打ち込むとは思っていませんでした。けれど、現実は案外あっさり無職になったりします。朝、目が覚めてもやることがない。何もしていないはずなのに、疲れて動けない。社会から取り残されたような気がして不安が押し寄せる…。想像以上にしんどいです…。
このページにたどり着いたあなたも、今、少し疲れて立ち止まっているのかもしれません。そんなあなたに、心理職としての視点も交えながら、「無職期間の心の整え方」をお伝えします。
どうすれば自分の心と向き合い、未来に向けて少しずつ行動できるのか、そのヒントを一緒に探していきましょう(関連項目:退職代行を考える前に──心理的視野狭窄とメンタルヘルス不調への理解)。
メンタルヘルス情報配信中!友だち登録どうぞ!
仕事を辞めて時間はあるはずなのに、なぜか何も手につかない。焦りだけが募る。
それ、実は自然な反応です。
心理学では、役割の喪失を「ロール・ロス(role loss)」と呼びます。
人は社会の中で様々な「役割」を担っており、「職業的役割(職業人としての自分)」もそのうちの一つです。職業的役割は「自分の能力を社会に還元し、評価され、対価を得る」という点で、自己効力感・自尊感情・アイデンティティ形成と深く結びついています。そのため、「無職になる=職業的役割を喪失する」と自己効力感・自尊感情・アイデンティティの形成にゆらぎが生じます。
職業人生が長かった方は特に、定職についていない状態を「恥ずかしい」と思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
京都大学の調査(2014)では、仕事を失うことで「自分とは何者か」という自己認識の不安定化を招き、抑うつや不安感を引き起こすことがわかっています。さらに、失業中は「自分には何もできない」という自己効力感の低下が生じやすく、同時に「社会に貢献ししていない自分は社会的に価値のない存在だ」と感じやすいため、社会的烙印を押された感覚や孤立感を増幅せることがわかっています(高橋,2012)。
上記に加えて、無職になり仕事に行かなくなると、必然的に社会との接点が少なくなります。特に人との接点が減ることは、予想以上にメンタルに影響します。ある研究によれば…社会的孤立は慢性的なストレス反応を引き起こし、ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌が高めるそうです。生物学的に考えても不安が強まりやすくなるのです(Heinrich & Gullone, 2006)。
──要するに、「今のあなたの状態はおかしくない」のです。
ここでは、心理学の概念をいくつか紹介しながら、無職期間に陥りやすい状態を説明します。
「今の自分は何者なのか分からない」
社会的な役割が消えることで、自己認識がぼやける状態です。心理職の間でも、離職直後に多く見られる心の揺れです。
「何をしても意味がない気がする」
これは、繰り返し努力が報われない状況で学習される「無力感」。転職活動がうまくいかない、周囲と比べて焦る…そんなときに起きやすい現象です。
「働いてない自分はダメだ」
これは極端な二元論思考で、うつ傾向や自己評価の低下に関与します(関連項目:【精神科医監修】認知のゆがみの治し方|心のコリほぐしましょう!)。
ポジティブ心理学では、つらい経験に「意味」を見出すことがしなやかな心を作る鍵だとされています(Park, 2010)。「この休養期間が、自分にとってどんな意味を持つのか」を振り返る時間を持つだけでも、心の整理が進みます。よく治療が進む中で「その時は辛かったけど、今回のことにはこのような意味があったんだ」とお話しされる方を目にします。そして以前の自分よりもさらにパワーアップされる方も多いです。
なんの理由もなく無職になった人はいないはずです。この失業期間はあなたにとってどのような期間だといえますか?
「自分には何もできない」と自己効力感を失ってしまった場合には、小さな達成体験を積むことをお勧めします。自己効力感というのは、「行動が結果を生み、その結果が自信となる」というサイクルにより生み出されます。たいそうなことをする必要はなく、ちょっとした家事、読書、散歩の記録など、達成できる小さな行動から積み重ねていきましょう(Bandura, 1997)。
社会的つながりは、回復のスピードと深さを大きく左右します。友人とのメッセージ、SNSでのコメントのやり取り、匿名のオンラインコミュニティなど、それだけでも、孤独感は軽減されると科学的に示されています(Holt-Lunstad et al., 2015)。見方によっては今まで繋がれなかった人と繋がるチャンスかもしれません。
私たちは時に「真っ直ぐな人生」を望みますが、VUCA時代において、望んだ通りの「真っ直ぐな人生」を歩める人の方が珍しいのではないでしょうか。職業についても同じです。どんな人にも、足を止める時期はあり、それは必ずしも本人の意思では選べないこともあります。
ブラック企業に勤めて心身の調子を崩した友人の「退職したいけど、人生のレールから外れる気がして踏み出せない」という話をよく思い出します。生きていくための資金源が一時的に途絶えることは、生命の危機であり生物として不安や焦りを覚えるのは当然で、自分が無職なってみて強く共感しています。
一方で、こんな気持ちも湧いてきました。レールを外れることはよくないことなのでしょうか。そもそもレールから外れるという言葉は正しいのでしょうか。
──無職は“失敗”ではなく、“変化の通過点”
あなたが今感じている停滞感や不安感は、きっとこれから新しい道を歩むための地ならしの期間です。レールから降りた先に見える世界は案外地獄ではないかもしれません。
…とはいえ、「まあどうにかなるでしょう」と、現実と向き合わずに楽観し、ただただ流れる時に身を任せることもまた違うのが難しいところです。
生きていくこと自体、シビアな世の中になっている現実があり、「ゆっくり考えよう」と悠長なことを言っていられないという状況の方もいらっしゃる中で、ポジティブな側面のみを強調してしまうのは無責任だと考えています。ただ、大切なのは不安をなかったことにするのではなく、「それでも今は立ち止まることに意味がある」となぜ今の状態になったのかを考え、自分と向き合うことだと思います。
と、現在四捨五入すると無職状態の私が自戒もこめて申し上げます笑
そして、なかには「まだ向き合う気力が湧かない」「無職になったらどうなってしまうのか、という不安で心身ともに限界なのに仕事を辞める決断ができない」という方もいらっしゃると思います。そのような方に向けて、心身の回復に関する記事や、失業後の制度に関する情報も徐々にお伝えしたいと思っていますので、一緒に頑張っていきましょう。
参考文献