2026年2月6日


初回カウンセリングをご希望の方はこちら
オンラインカウンセリングログイン
資料ダウンロード
タグ : chico(公認心理師・臨床心理士) , メンタルヘルス
2025年3月21日
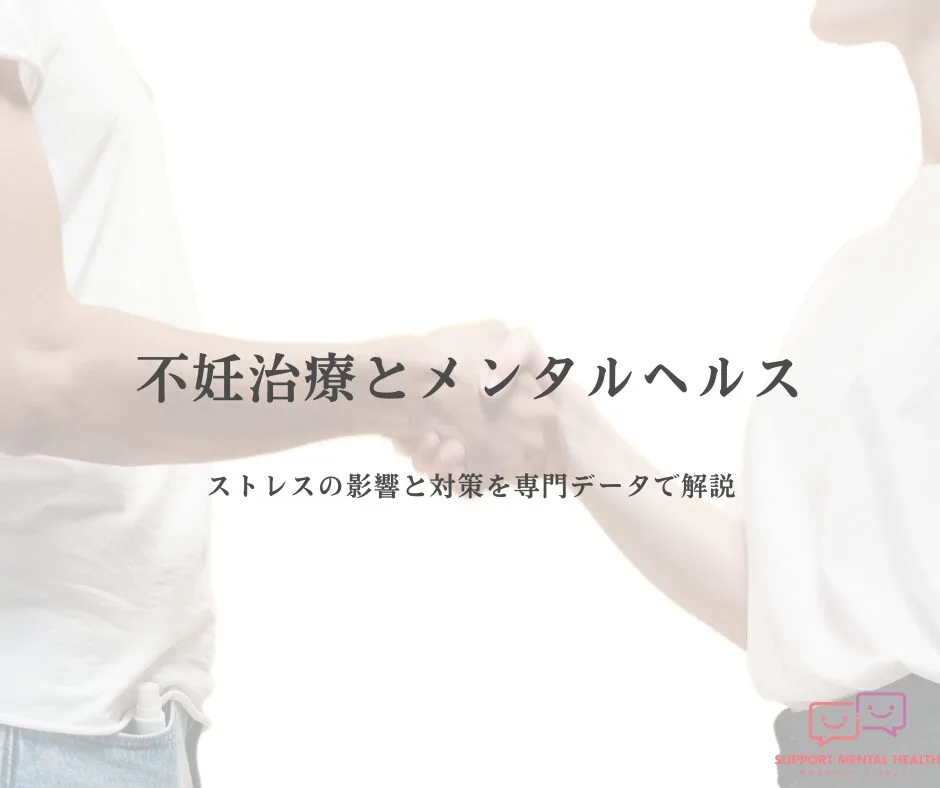
目次
皆さんは不妊治療にどのようなイメージをお持ちでしょうか。希望に満ち溢れたもの?それとも…?
今回は、不妊治療に取り組む方のメンタルヘルスについて、研究データをもとに解説していきます。
メンタルヘルス情報配信中!友だち登録どうぞ!
不妊とは「妊娠を望む健康な男女が避妊をしないで性交をしているにもかかわらず、一定期間妊娠しないこと」と定義されます(日本産婦人科学会による)。女性側に原因があると誤解されやすいのですが、実際のところ不妊原因の割合は男女1:1と言われています。
不妊治療は、婦人科や不妊外来などで、まず検査を行い、その結果をもとに治療を進めていきます。詳細な説明は省きますが、「タイミング法」、「人工授精」、「体外受精」、「顕微授精」などの方法があります。
日本では4.4組に1組が不妊の検査・治療を経験したことがあるそうです(※1)。しかし残念ながら、不妊治療をしても全員が出産に至るわけではありません。体外受精によって子供を授かる割合は12.9%(日本産婦人科学会による)。治療とはいえ、「これをやれば必ず妊娠できる」という方法は存在しないのです。
不妊治療に取り組む人には様々なストレスがかかり、心身の不調が生じることも珍しくありません。正式な診断名ではありませんが「不妊うつ」「妊活うつ」という言葉もあるほどです。
研究データを見てみましょう。
|
確率の差はありますが、性別や治療期間に関わりなく、どの人にでもメンタル不調が生じる可能性があるのです。
不妊治療に取り組む人には、具体的にどのようなストレスがかかるのでしょうか。2023年に国立成育医療研究センターが発表した「4つのネガティブなストレス要因」(※2)をもとにまとめてみます。
不妊治療の特性上、「頑張っても報われない」ということが当然のように起こります。そして次また頑張っても、必ず妊娠できるわけではありません。いつまで頑張ればいいのか、いつ諦めたらいいのか、誰にも答えが分からないのです。
「いつやめるか」という選択もあれば、「次にどの治療法を行うか」という選択も続けていく必要があります。自分の選択で将来が変わってしまうかもしれない…プレッシャーは計り知れないことでしょう。
このストレスは自分以外の要因に向けられています。代表的なものを見ていきましょう。
本来、不妊治療にはパートナーと二人三脚で取り組みたいものです。しかしながら、パートナーが一番の悩みの種となることは珍しくありません。
例えば…
不妊治療には様々な選択肢があります。そのすべての選択が二人で合致することはほとんどないでしょう。相手の行動に不満や当惑を覚えることも考えられます。
月1回の排卵日にかける思いと、自然な雰囲気で性行為をしたいという思いが二人の間でぶつかることがあります。排卵日に勃起不全になってしまうケースも少なくないそうです。
相手の気持ちを察するがゆえに、話し合いを避けてしまうことがあります。「相手が協力的だから終わりにしたいと言えない」、「自分は続けたいが相手が辛そうで何と言ったらいいか分からない」などです。
仕事との両立も大きなストレスとなり得ます。治療法によっては頻繁に通院する必要があり、1ヶ月に10日以上の受診が求められることもあります。また排卵のタイミングなどにより、急に受診日が変更になることも。不妊治療をする女性の4人に1人は退職しているというデータもあるほどです(厚生労働省による)。退職までいかずとも、職場の理解を得るのに苦労されている方は多いのではないでしょうか。
人間誰しも、自分自身の将来の姿について何となくイメージすることがあると思います。仕事をバリバリしている自分、趣味に打ち込んでいる自分、家族と過ごしている自分…皆さんはどうですか?そのイメージのなかに子どもがいる場合、不妊治療に取り組んでいる方はどうなるでしょうか。「いつかそうなって当然」と無意識に思っていた自分の姿が壊されていく体験をすることになります。自分に自信がなくなり、自分を否定するようになっていきます。
友達の妊娠を素直に喜べない、妊婦を見ると嫉妬する、SNSの子どもの投稿を見て怒りを覚える、親戚の集まりに行けない…こういったことがあっても不思議ではありません。ですが、そう思ってしまう自分を責めてしまうことがあるようです。
2022年4月から不妊治療の保険適用範囲が拡大し、経済的負担は以前に比べて軽くなりました。しかし回数や年齢の制限などがあります。治療が長期化したり、高度な治療法に取り組んだりすると、治療費は高額に。そして焦りや不安がのしかかります。
不妊治療中の日本人男性を対象に、どのようなケアがほしいか聞いた調査(※4)があります。50%以上の男性の回答には次のようなものが含まれていました。
また、体外受精または顕微授精の治療中、男性は女性よりも社会的な孤立が高まるという報告もあるそうです(※3)。治療の詳細がパートナーから明かされない、パートナーにどう寄り添ったらいいか分からず困惑する、などのことが推測されます。
強いストレスがあると、性別にかかわらず、妊娠に関わるホルモンの分泌にも悪影響が出てしまいます。やれるところから少しずつ対応していきましょう。
職場に不妊治療のことを伝えている場合、考慮してほしいことを具体的にしておくと、相手も対応がとりやすくなります。また誰にどのように伝えるかも考えておくと◎。病院で書いてもらう「不妊治療連絡カード」も活用できます。伝えていない場合は、リモートワークやフレックス制など働き方の調整、あるいは夜間診療や休日診療を行っている病院への転院などが検討できます。
ここまで読んできていただいて分かる通り、不妊治療にはストレスが付きまとい、メンタル不調が生じても全くおかしくありません。自分を責めず、リラックスできることをしたり、冷静に気持ちや考えを書き出したりしてみましょう。良く寝て、良く食べて、少し運動する。日々の生活を回していくことも立派なセルフケアの1つです。
不妊治療中に、臨床心理士のカウンセリングを受けた人のほうが、妊娠に至っていたとの報告があります(※5)。カウンセリングによってストレスが解消され、不妊治療を継続できたためだと考えられます。通院先の病院でカウンセリングが行われていれば、一度受けてみるのはいかがでしょうか。
ちなみに、東京都には「不妊・不育ホットライン」が設置されています。ぜひお住まいの自治体でも相談窓口を調べてみてください。
引用文献
※1 東京都福祉局(2024)いつか子供がほしいと思っているあなたへ
※2 国立成育医療研究センター(2023)高度不妊治療を受ける女性が感じるストレス要因が明らかに(プレスリリース資料)
※3 ESHRE 心理・カウンセリングガイドライン作成グループ (2015)不妊とMAR(医療的に補助される生殖)における日常的な心理社会的ケア一生殖医療スタッフのためのガイド
※4 Asazawa K, Jitsuzaki M, Mori A, et al.(2018)Supportive Care Needs and Medical Care Requests of Male Patients during Infertility Treatment. Open Journal of Nursing. (8) pp.235-247
※5 小泉智恵・田中久美子・森本 義晴(2023)不妊治療初診時期の心理カウンセリングと治療中断、妊娠との関連 : コックス比例ハザードモデルを用いた後ろ向きコホート研究の試み 日本生殖心理学会誌9巻1号 pp.20-26
参考文献
【執筆】 chico(公認心理師・臨床心理士) |